前期量子論
光の研究は古くから行われていました。 ニュートンも光の研究を行っており、1704年に著作「光学」を刊行しています。 この頃から光は粒子だという説と波だという説があり、ニュートンとしては光は粒子であるという立場を取っていました。
1801年トーマス・ヤングは二重スリットを用いた光の干渉実験を行い光が波の性質を持つことを示しました。 19世紀中頃にはマクスウェルが光は電場と磁場の波であることを発見します。
ところがその一方で、光を粒子と考えなければ説明できない現象も見つかってきたのです。
黒体放射
19世紀後半にはドイツを中心に鉄鋼業が盛んになります。 鉄を熱するときに使う溶鉱炉の温度は熟練した職人が目で見て経験的に判断していました。 発せられている光の色を見れば温度がわかるのです。 では正確にどの温度のときにどんな色に見えるのでしょうか。 この疑問から黒体放射もしくは空洞放射と呼ばれる現象が研究が始まります。
夜空を眺めてみると、温度が低い星は赤っぽく光り、温度が高い星は白っぽく光っています。 星の温度が高いほど波長が短く振動数の高い光が多く出てきます。 9000℃くらいではさまざまな波長の光が混じるため白い色に見え、さらに10000℃を超えてくれば青白く輝きます。
これは星に限った話ではありません、どんな物体も温度が上がれば必ず光を出します。 とりわけもともとが黒い物体や真っ暗な空洞から漏れ出る光は、どんな温度のときにどんな振動数の光がどれくらい出てくるかは決まっています。 溶鉱炉がどんな材質で作られていようが、同じ温度であれば同じ分布で光が出てくるのです。
レイリーとジーンズは、温度と光の振動数の関係を「エネルギー等分配則」から考えました。 溶鉱炉の中には様々な振動数の電磁波が存在しますが、確率的にどの振動数にも均等にエネルギーが配分されるはずです。 そこから導かれた式がレイリー・ジーンズの式です。
$ $$\displaystyle Idν = \frac{8πν^2kT}{c^3}dν$
$I$ がエネルギー密度、$ν$ は光の振動数、$k$ はボルツマン定数、$T$ は温度、$c$ は光速度です。
レイリー・ジーンズの式は振動数が低い領域では実測値とほとんど一致します。 このことからもエネルギー等分配則の考え方は基本的には間違っていないはずです。 ところが振動数が高い領域でこの式は実測値とまるで合わないのです。
プランクのエネルギー量子仮説
1900年プランクは、黒体放射の実測値と一致する式を発表します。
$\displaystyle Idν = \frac{8πh}{c^3}\frac{ν^3}{e^{hν/kT} -1}dν$
この $h$ は $6.626×10^{-34}$ という非常に小さな定数です。 しかしなぜこのような式が成り立つのかは不思議でした。 エネルギー等分配則から理論的に導かれるのはレイリー・ジーンズの式です。 しかし現実に成り立っているのはプランクの式ですから、エネルギー等分配則以外に何か隠れた要因があるのは間違いありません。
プランクはこの式の意味するところについて考えました。 そして光のエネルギーが $hν$ の整数倍の値しか取れないと仮定すればこの式が導かれることに気づきしました。 光のエネルギーはすべての振動数に均等に分配されるわけではなく、振動数の高い光にはエネルギーが分配されにくくなるためこの式が成り立ちます。
ですが現実問題として光のエネルギーが $hν$ の整数倍の値しか取れないなどという理屈はありません。 当時の科学者たちも、プランク自身もまだこれの意味する事はわかりませんでした。
アインシュタインの光量子仮説
金属の表面に光を当てると荷電粒子が飛び出す「光電効果」という現象についても謎が残されていました。 振動数の低い光を大量に当てても電子は飛び出しませんが、振動数の高い光を当てれば電子が飛び出します。 光が強いほどたくさんの電子が飛び出しますが電子1個あたりの運動エネルギーに変化はありません。 これらの現象は光が波だとするとうまく説明できません。
1905年アインシュタインは光量子仮説と光電効果について発表します。 光がまるでエネルギー $hν$ の粒子のように振る舞うと考えて光電効果を説明したのです。 エネルギーの低い粒子がいくつ当たっても電子は弾き出されませんが、 エネルギーの高い粒子が当たれば当たった数だけ電子が弾き出されます。
しかし光には屈折や回折や干渉などの現象があり波として振る舞うことも確かです。 この段階ではまだ光が粒子であるという仮説は現実味を帯びていません。
ボーアの量子条件
この頃から原子の構造についての模索が始まりました。 1897年電子を発見したジョゼフ・ジョン・トムソンは、 1904年 正の電荷を持った原子の中に負の電荷を持った電子が散らばっているというブドウパンのような原子モデルを考えます。

1909年ラザフォードはα粒子の散乱実験により、原子の中は隙間だらけであることを突き止めます。 そして1911年 正の電荷を持った核の周りを電子が飛び回っているモデルを考えます。 しかしこのモデルは当時の電磁気学でうまく説明できません。 飛び回っている電子は電磁波を放射してすぐに原子核に落ち込んでしまうはずだからです。

1913年ボーアは、原子が特定の波長の電磁波だけを放出したり吸収したりすることから、 電子はいくつかの決まった軌道しか取れないという仮説を発表します。 軌道が変わるときはなぜか飛び飛びに移り変わり、そのため出入りするエネルギーも飛び飛びになります。 そして最も内側の軌道を回っている電子はそれ以上内側に落ち込むことはありせん。 なぜこのようなことが起こるかは後にド・ブロイやそれ以降に発展する量子力学によって説明されます。
コンプトン効果
1922年コンプトンは、物体にX線を照射して散乱したとき波長が長くなる現象について、 光がまるで粒子のように電子と衝突したと考えれば説明ができることを示しました。 光がエネルギー $E = hν$、運動量 $p = hν/c$ の粒子と考え、これが電子と弾性衝突したとして計算すれば実験結果と一致します。 これによりアインシュタインの光量子仮説は確かなものになりました。
もはや光は粒子か波かという議論に意味はありません。 あるときは波のように振る舞い、あるときは粒子のように振る舞うものと考えなければいけません。
ド・ブロイ波
ド・ブロイは、粒子である物質にも波の性質があるのではないかと考えます。 これはまるで突拍子もない意見のように感じますが、光子だけが説明のつかない不可解な存在と割り切ることはできません。 光子に限らず波と粒子を関連付ける何かがあるはずです。
1924年ド・ブロイは「ド・ブロイ波」あるいは「物質波」という考えを提唱し、 光子も含めあらゆる粒子は波のように振る舞うと予測、アインシュタインはこれに賛同します。 その振動数と波長は次の式になります。
$\displaystyle ν = \frac{E}{h}$
$\displaystyle λ = \frac{h}{p}$
$ν$ が物質波の振動数、$λ$ が物質波の波長
$h$ はプランク定数
$E$ はエネルギー 、$p$ は運動量
ド・ブロイ波は光以外の物質でも回折や干渉が起こる可能性を意味しています。 電子も波であると考えると、原子内の電子が特定の軌道にしか存在できないというボーアの量子条件も説明できます。
そしてこの波から粒子も説明できます。 現実の波は波長や振動数に微妙なずれがあります。 微妙にずれた波が重なり合えば、波が群を成して移動する「うなり」という現象が現れます。 我々はこのうなりを粒子として捉えていると考えたのです。 実際ド・ブロイ波の式からうなりの移動速度(群速度)を計算すると、粒子の速度と一致します。
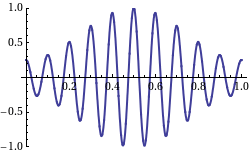
1927年のデイヴィソンらの実験では電子線でも干渉縞が現れることが確認され、ド・ブロイ波の存在が認められました。